はじめに
私は30代前半の時に子ども(当時、幼稚園児)と一緒に囲碁を始め、3年目で初段に到達し、現在5年が過ぎました。今でも楽しんでおり、囲碁を始めてよかったと思っています。
囲碁を新しく始める場合の囲碁の良いところや悪いところを、当時いろいろ調べたことや、囲碁を始めてから気づいたことを記事にしました。
- 囲碁の良いところ・悪いところ
- どんな人に囲碁が向いているか
- 囲碁と将棋の比較:新しく始める場合
囲碁の良いところ
- 盤面が広く自由に打てる
- 手筋がすごい、おもしろい、実践で打てると気持ちいい
- 成長を実感できる
1.盤面が広く自由に打てる
囲碁のおもしろさはなんといっても、盤面が広く自由に碁石を打てることです。
囲碁は相手との勝負なので、勝てるように打つには棋理にかなった打ち方が必要になりますが、それでも自分の好きな戦法を自由に選んで打つことができます。例えば、とにかく戦いを続けまくる打ち方、逆にできるだけ戦いを避けてお互いのんびり打つような打ち方、あるいは最初から隅や辺の陣地を取りにいき後で相手の大模様を荒らす打ち方、など自分の好きな&研究してきた打ち方ができます。
盤面が広いため、最初から最後までまったく同じ盤面になることはありえません。いつも同じような展開でつまらなくなる、なんてことはなく、毎局新しい発見(好手、ぽか、失敗、興奮、後悔、などなど)があり、飽きることがありません。
2.手筋がすごい、おもしろい、実践で打てると気持ちいい
手筋とは、より大きな効果を挙げることのできる着手を言います。要は、良い手、のことです。
囲碁にはいろいろな種類の手筋があり、それらをまとめた手筋本などで棋力向上を目指して勉強しています。
手筋本には自分では思いつかないような手筋がたくさん載っていて、答えを見るだけでも「こんなすごい手があるのか!」と感動ものです、まるでマジックを見ているかのようです。高段者向けの高度な手筋はまだまだ意味不明で理解できないものもありますが、自分の棋力upに応じて理解できる手筋が増えていきます。
また、そんなすごい手筋を自分の実戦で打てて勝てたときには、脳汁でまくり、とても幸せな1日になります。

図はウッテガエシという手筋。黒①と打った時点で、右下の白4子はもう取れています。
入門者が最初にびっくりする定番手筋ですが、自分の実戦で初めて打てたときは感動しました!

低段者になっても、自力では思いつかない手筋をみると感動します!
まだまだ飽きる気がしません。
3.成長を実感できる
私は囲碁のルールを全く知らない状況で始めました。囲碁のルールを理解して、「囲碁おもしろい」と思うまで1-2週間くらいかかったと思います。
ただ、それからはグングン上達していくのが分かります。なぜなら始めたての頃は、新しいコツをちょっと習得できると、それが盤面でたくさん出てきてうまく打てる場面を多く経験できるからです。


囲碁で上達するのに必要な知識量は、逆三角形のイメージですね。
最初の頃はちょっとしたコツをつかむとグングン強くなれます。
逆に、ある程度強くなると、さらに強くなるには膨大な知識、経験が必要になってきます。
- なかなか解けなかった手筋本・詰碁本が、スラスラ解けるようになる。
- インターネット碁で級位・段位が上がる。
- 地元の囲碁大会で優勝した(もちろんハンデ戦)。
自分の成長を実感できる上記のようなことを、最近経験したことありますか?
年をとってからでも囲碁を始めると、特に全くの0からのスタートの場合、伸びしろが大きくある分、成長していることを実感できて嬉しいですよ。
囲碁の悪いところ
- 囲碁の楽しさが分かるまでが大変
- 1局に時間がかかる
- 囲碁人口が減少している&おじいちゃんのイメージ
囲碁の楽しさが分かるまでが大変
囲碁は入門が最大の難所といわれるものの、一度覚えてしまえば一生続けられるすばらしい趣味になります。
『はじめての囲碁の教科書』 はじめに より引用
囲碁はルール自体は簡単で、かつ「自由に打ってよい」はずなんですが、盤面が広過ぎて何を指標に打ったら良いのか?何を争っているのか?、どこがおもしろいのか?(これは人によって異なるかもしれません)を理解していないと面白さを全く感じられません。囲碁を始めようとしても、断念してしまう人が一定数いるのもうなづけます。
私の場合、囲碁を始めて1-2週間のころ、9路盤(小さい碁盤)でネット対局しているときに、大きく広げて自分の陣地だと思っていた内側に相手に入られて、逆に陣地を作られて負けてしまった!ことを経験して、気づきました!





単純に陣地を広げれば良い
ってわけではないんだ!
相手に内側に入られないように、でも陣地の広さで勝てるように、ギリギリの範囲で囲わないと勝てないんだ!と対局で気づかされた時に「囲碁って奥深い!」と気づき、囲碁の面白さの一部が分かりました。
囲碁おもしろい!と思う部分は人によって違うかもしれませんが、「どうすれば勝てるのか」を自分で考えられるようになることで囲碁のおもしろさが分かるようになると思います。
1局に時間がかかる
囲碁の欠点として、1局を終えるのにどーしても時間がかかることが挙げられます。
囲碁の正式な盤である19路盤の場合、短くても20~30分、長いと1時間以上かかってしまいます。盤面が広く複雑になるほどおもしろいなぁと思うのですが、19路盤で良い手をよ~く考えて打つとどうしても時間がかかってしまいます。
私の場合、囲碁の対局を楽しむには時間をかけたいのですが、1局1時間と考えると億劫になってしまい、19路盤での対局は休日に1,2局打つくらいにとどめています。
ただ、9路盤や13路盤といった小路盤でのネット対局も充実しており、それぞれ10分、15分くらいで1局が終わるので、平日は小路盤をたくさん打っています。
囲碁人口が減少している&おじいちゃんのイメージ
囲碁人口は年々確実に減っていっているようです。
碁会所や大会に行くと、おじいちゃんが多いです、いやほとんどです。
周りに囲碁のルールを知っている人はどれくらいいるでしょうか?おじいちゃん世代以外ではほとんどいないのではないでしょうか?
将棋なら子どものころ良く指していた、コマの動かし方は知っているよ、という方は多いと思います。
囲碁については、「陣地取り」というイメージくらいは知っていても、囲碁の局面を見てどこが面白いのか分かる人はそうそういないと思います。囲碁について話しができる人が身近にいないのは、やはりさみしいですね。
囲碁はどんな人に向いている?
- インドア派で知的ゲームが好きな人
- 親子や夫婦など、身近に一緒に始める人がいる人
インドア派で知的ゲームが好きな人
囲碁が向いている人は、ずばり、知的ゲームが好きな人です。
そのままなんですが、戦略ゲームやパズル系が好きな人に向いています。
私自身も、大戦略、ファイアーエムブレル、カルドセプトといった戦略系ゲームが大好きで子供の頃よくやっていました。
また屋内で完結するのも良い点です。家でネット碁をするときも、大会に参加するにしても、よしやるぞ~って思った時に天気が悪いから今日は無理!なんてこともありません。囲碁なら少ない休日に天候に左右されず確実に楽しむことができます。
ちなみに、今までやったことのある戦略系ゲームの中で、囲碁が最も奥深く、楽しい!と私は思っています。
また「詰碁」といって、将棋でいう「詰将棋」のような、局所の最善手を考える問題があります。「詰碁」は囲碁の上達にはかかせないものですが、棋力向上のためではなく単純に「詰碁」だけをパズル問題を解くように楽しんでいる方もおられるようです。
親子や夫婦など、身近に一緒に始める人がいる人
こどもと一緒に始めたり、夫婦で始めるなど、身近に一緒に囲碁を始める人がいる方にも(当然、個人の向き不向きはありますが、)囲碁は向いていると思います。
なぜなら、多くの方々の場合、お互いが囲碁のことを全く知らない状態なので、始めるときに差がありません。
他の趣味の場合、例えば将棋やウォーキングや何らかのスポーツなり、親子での経験の差や男女による体格・運動神経の差などが多くの趣味であると思います。囲碁は、多くの方が経験がないと思うので、一緒に始める場合はお互い0からのスタートで、お互いが助け合って上達出来ると思います。
また、お子さんが囲碁を始めると、県代表として全国大会に参加できる可能性もありますよ、ライバルが少ないので。都会の場合は子供でもかなりの実力がないと代表になれませんが、地域によっては小学生の代表者がいない県もあるので、ちょっと強くなれると全国大会に出場できる可能性がでてきます
私の場合も、当時幼稚園児だった子どもと一緒に楽しめる趣味として、囲碁を始めました。
ルールについては大人の私の方が早く理解して、子どもに教えてあげていました。しかし、囲碁の強さについては1ヶ月くらいのうちにあっという間に抜かれ、以降は子どもが私に囲碁を教えてくれるようになりました。ちなみに、子どもはまだ小学生なのに既に六段に達していて、全国大会にも出場できたことがあります。
囲碁と将棋の比較:新しく始める場合
知的ゲームが好きなら囲碁ではなくて将棋でも良いのでは?
そーです、将棋でも良いんです。
でも、私も囲碁を始める前に、囲碁と将棋をどちらにしようか色々と調べた結果、囲碁を選びました。
| 囲碁 | 将棋 | |
| 人口(レジャー白書2021年) | 180万人 △ | 530万人 ◎ |
| 序盤の自由度 | とっても高い 楽しい ◎ | 同じような指し方が多い △ |
| 終盤の派手さ | ヨセは地味だけど楽しい 〇 | 派手 1手差勝負が熱い ◎ |
| ハンデの付け方 | 置き石、コミ ◎ | 駒落ち △ |
| 国際戦 | あり ◎ | 日本国内のみ 〇 |
| 年をとっても楽しめるか? | きっと◎ | う~ん、△ |
まず、△~◎は私の主観です。また、囲碁よりの内容であることを、将棋勢の方々にお詫び申し上げます。
人口
将棋の方がプレイ人口が多いため、メディアへの露出や本、youtube動画などコンテンツは圧倒的に多く、将棋の方が良いように思います。また囲碁の場合、人口が減少しているだけでなく、高齢者の愛好家が多く若者は少ないようです。
ただ、囲碁もネット対局を含めば対局に困る事はないですし、プロ棋士のyoutube解説やタイトル戦解説なども多くあり、将棋の方が良いなぁ~と思うことは、今のところあまりないです。
序盤の自由度・終盤の派手さ
序盤
序盤の自由度は圧倒的に囲碁の方が楽しいと思います。将棋の場合、ある程度強くなると定跡暗記が必須になり、序盤は同じような盤面が多くなるようです。また定跡を外してしまうと一瞬で負けてしまうこともよくあると聞きました。一方で、囲碁の場合は、序盤で多少のミスをしても他の盤面でまだまだ取り返せることもありますし、部分的に上手に打てていた時には勝負に負けていても満足できる場合もあります。
終盤
将棋の終盤はとてもダイナミックで、1手の差で勝敗が決まることも多くスリリングな展開も多いです。
囲碁の終盤はヨセと言って、陣地の境界線を確定していきます。観戦する立場からすると、かなり地味なので見ごたえが少ないと感じます。しかし、ヨセは強い人と弱い人で実力の差が如実にでてくる分野なので、勉強すると確実に強くなる分野と言われています。ヨセは地味ですが勉強のしがいがありますし、プロの見事なヨセを見ると感心します。
ハンデの付け方
対局者に棋力の差がある場合、囲碁では「置石」でハンデをつけることができます。
置石はその名の通り、最初から石を多く置いた状態で対局を開始するのです。棋力の差に応じて2子~9子(石の数は1子いっし、2子にし、と数えます。)くらいで調整します。同じ上手(「うわて」自分より強い人)を相手にして置石が減っていくのも成長を実感できる瞬間です。
また囲碁は陣地の多さを競うので、その陣地を最初からハンディキャップとして多く設定する(コミ)ことでハンデを調整することもできます。
一方で、将棋の場合、棋力差の調整が難しいようです。最初からいくつかの駒が少ない状態で対局をする「駒落ち」というハンデ設定がありますが、駒の落とし方の微調整がうまくはいかないようです。
同じくらいの棋力の方と対局する場合はハンデは不要ですが、始めたばかりのころはどうしても棋力差があると思いますが、囲碁の場合は「置石」というぴったりなハンデの付け方があるので、始めたばかりのころでも、上達しても楽しめると思います。
国際戦
囲碁のメリットとして、海外にもプレイヤーがいることが挙げられます。プロ棋士の国際戦もいくつもあり、日本棋士を応援するのも囲碁ライフを楽しむ1つの方法です。またアマチュアプレイヤーも海外に多くいるので、インターネット碁での対局は日本人のみでなく、海外の相手とも楽しむことができるのも魅力になります。
年を取っても楽しめるか?
最後の比較は、「年をとっても楽しめるか?」です。私が新しい趣味に囲碁を選んだのはこの比較が大きかったです。
どちらも続ける分には問題ないと思うのですが、将棋はどうしても定跡暗記ゲームの側面があります。定跡を覚えていないと勝負にならない、でも定跡はどんどん増えていく。いろいろと調べている内に、将棋は年をとるとなかなか勝てなくなる、楽しくなくなる、という意見を多く目にしたのです。
一方で、囲碁の場合も序盤の打ち方である定石(将棋とは漢字が異なります)はありますが、多少定石を間違えてもそれだけで勝負が決まることは少なく、また周りの配石によっては定石外れの方が好手になることもあるくらいです。
要は、ある程度強くなり、ある程度年をとっても、囲碁の場合はずーっと楽しむことができるのでは!と思い至りました。
だって、囲碁打っているのは、おじいちゃんばっかりでしょ!おじいちゃんになっても囲碁は楽しいんですよ、きっと!!!
まとめ
- 盤面が広く自由
- 成長を実感できる
- 一緒に始める人がいればなお楽しい
- 年をとっても楽しめる、きっと
私の体験談を踏まえ、私なりに囲碁の良いところ、悪いところ、をまとめました。
囲碁をするのか、将棋をするのか、はたまた別の何かを始めるのか?
人それぞれだと思いますが、せっかく囲碁に興味をもったのなら、囲碁を始めて見ませんか?
楽しいですよ、囲碁。
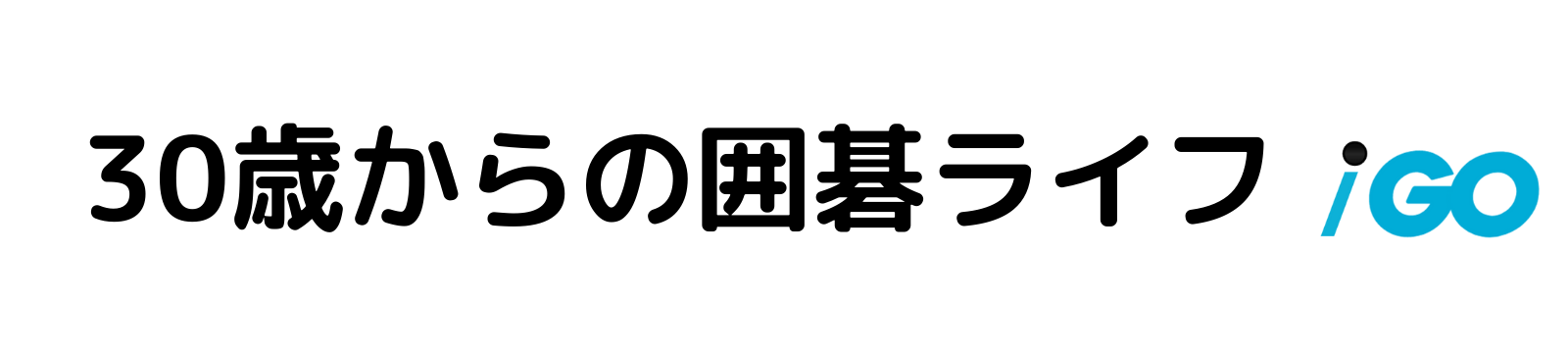
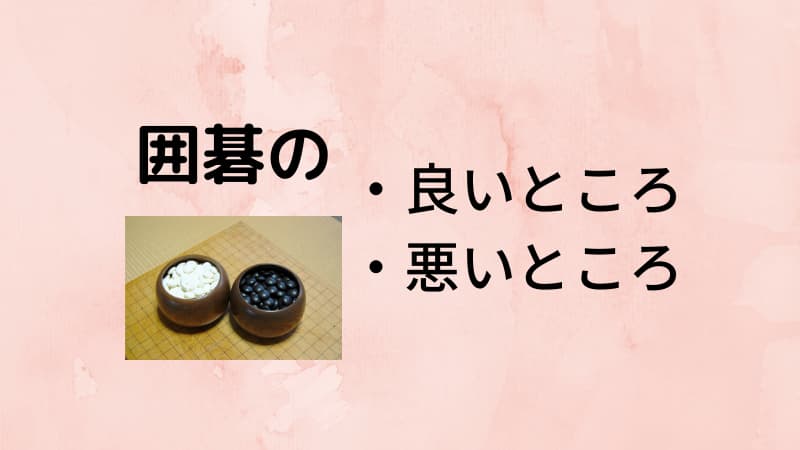
コメント